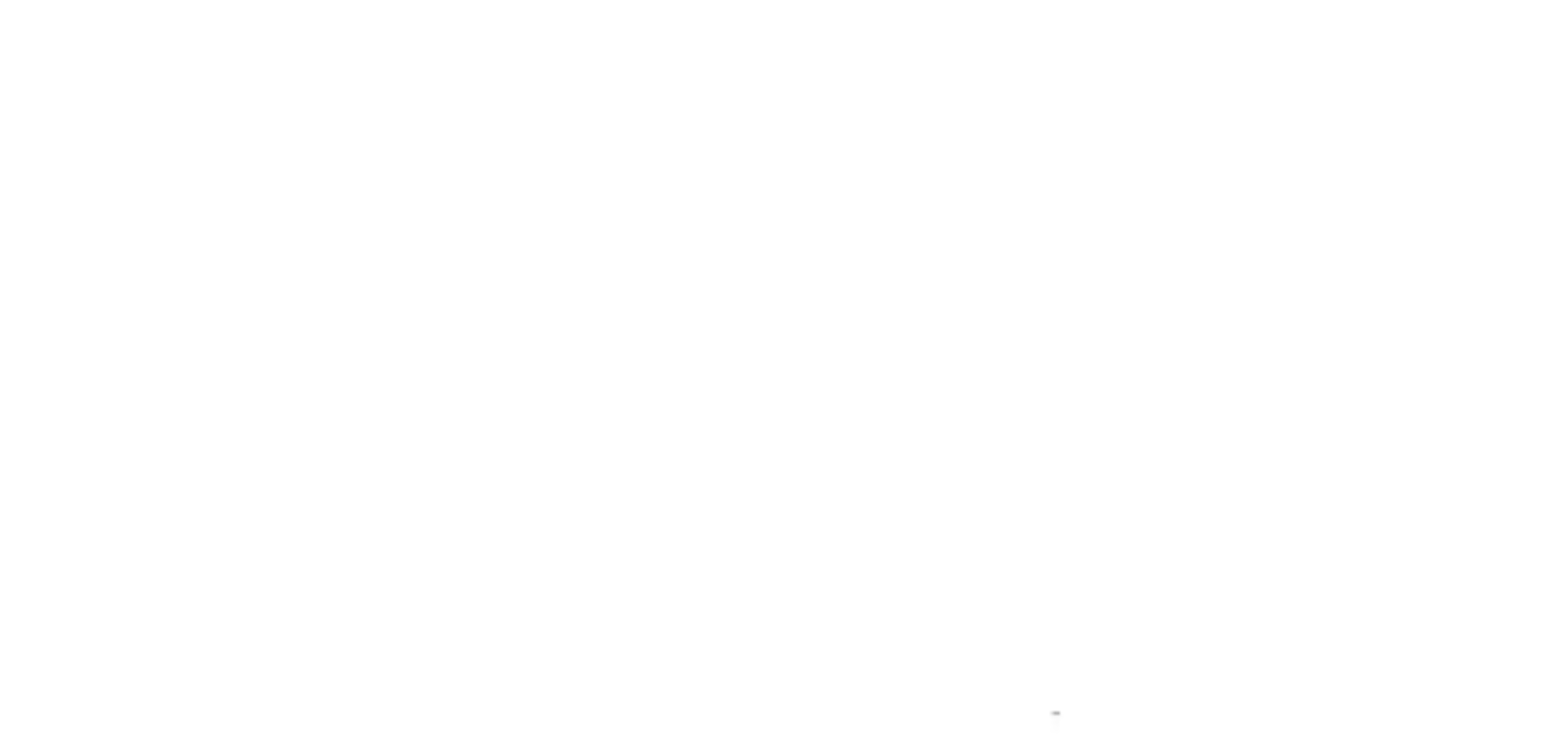しばしば絵を仕事にしているのかと問われるが、実際、今日に至るまでに絵を通して受け取った金銭は自作のグッズや作品集の販売と、個人的な依頼のみ。
ここ以外で一切描いていない。仕事は絵とは関係ないところで細々とやっている。内情のおかげでロクに働けないのは甘えだと何度も思っている。未だにたまに思う。
しかしどれだけ自分を卑下しようが何も変わらず、世界は滞りなく回ることも知っている。
自分の不毛な足掻きを横目に、軽々しいステップで進む大勢の背中を何度も見送った。
ひとり家でこもっている間にも季節は過ぎた。
周りは見知らぬ新しいものに目を輝かせて生きている。
その間自分はグラスに移る自分をただひたすらに見ていた。死にたい。
夏、瓦解を先送りにする特効薬を求めて外に出るとあまりの暑さに冷や汗が止まらなくなり、水路のそばでうずくまっていた。
澱みに落ちた葉はただ静かに浮かぶばかりで、何も面白くない。
そのうちにも電車は何本も行き交った。
情けない己の、さらに情けない表現欲が、いつからか描く絵そのものにのっかっている。
これを食っていくために利用できるわけがない。
矜持、そこにうまいこと希死を乗っけているような酷いものだ。
だからこそ、ここには誰も入れられない。
自分と自分のように不器用な人のものだけでいい。
頭も心も固まったセメントみたいに最悪の見た目と性質だと思う。
光の正体がプラスチックの反射であった時に、心のうちにあるものは酷くとも、事実という点において最初からどこにも嘘はない。
盲目であった事実が空に放たれ、瞬きのうちに硬い地面に落下。響く乾いた音のような無慈悲によって、ほとんどの物事に対する説明は付いた。
いつも自分以外が正しいと感じている。
先にも後にも、ここには何もない。
季節はまた巡った。じきに春だ。
希望の様相をした南風が、心を土埃の内に隠すから、いつも春はどこか他人事のように感じられる。